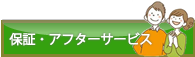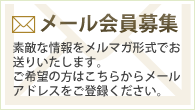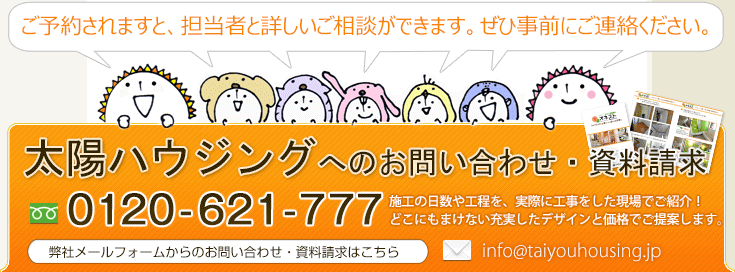床
1. フローリング
日常のお手入れ
- 板張りの床は水が大敵。日常のお手入れは、なるべく水を使わないことが基本です。やむを得ず濡れた雑巾などを使った場合は、しっかりと乾拭きをしてください。
- 大きなゴミやホコリは、ほうきや掃除機で取り除きます。掃除機等で取り除けなかった小さなホコリや細かな汚れは乾拭きしましょう。さらに念入りに行いたい場合は市販の床用お掃除シート等で拭き取ります。
- 水や醤油などをこぼしたときは、すぐに拭き取るようにしましょう。その際は念入りに乾拭きを行ってください。
※木質床材の板と板の継ぎ目の部分や、表面塗装が劣化した部分から水がしみ込むと表面材の割れやはがれが発生してしまいます。水・醤油などをこぼしたら、乾いた雑巾などですぐに拭き取りましょう。 -
乾拭きしても落ちない汚れは、水で濡らし固く絞った雑巾で拭き取り、きれいになったら、乾いた布で水分を十分に拭き取ります。さらに落ちにくい汚れには、住居用洗剤(木質床材に使用できるもの)を薄めた液で濡らした雑巾を固く絞って拭き取ります。この場合も汚れが落ちた後、乾いた布で水分をじゅうぶんに拭き取ります。
※汚れ取りには、シンナー、除光液、塩素系洗剤、酸素系洗剤を使用しないでください。(色落ちの原因となります。)
【ワックス掛け】
擦りキズ・シミの予防や、ツヤを保つために定期的にワックス掛けをしましょう。転倒防止のため、必ずすべり止め剤入り木質床用ワックスを使用しましょう。樹脂ワックスを用いる場合は厚く塗りすぎると、歩行時にワックス皮膜の割れる音が発生することがあるのでご注意ください。
【ワックス掛け時期の目安】
水性ワックス:2~3ヶ月に1回
樹脂ワックス:2~3ヶ月に1回
油性ワックス:1ヶ月に1回
※無垢の単一材の場合は1カ月に1回を目安にしてください。
※上記の時期は一般的な目安です。使用するワックスにより多少異なるため、事前に取り扱い説明書をご確認ください。
補修方法
| 小さい切り傷や 引っかき傷 |
同色のマジックペン等を塗ってからワックスで磨きます。市販のフローリング用キズ補修クレヨンなどを使ってもよいでしょう。 |
|---|---|
| 小さい床のへこみ | パテかエポキシ系の重填材で埋めてからフローリング塗装用修正剤で着色します。 |
| 大きい床のへこみ | (1)床材と同じ材質の板で埋木します。 (2)埋木のすき間は木工用パテで補修してください。 |
| そり | 縁甲板など無垢の単一材を使用したものは、そりが生じてもわずかであれば心配ありません。(季節により乾燥収縮が起こります。)その他の場合は“リフォーム倶楽部オネスト”までご相談ください。 |
| 床鳴りがする、きしむ | 長い間置いたピアノやタンスなど、重い家具を移動した後などでは、床鳴りやきしみが起こる場合があります。“リフォーム倶楽部オネスト”にご相談ください。 |

- 熱いものを直接、置かないようにしましょう。
- 電気カーペットを敷く場合には、床材の劣化を抑えるため、断熱材のある専用シートを下に敷いてお使いください。
- 木材は重い家具などの重量が一点に集中すると、その部分がへこんでしまいます。ピアノなど重いものの脚部には、小さな板などを敷き、重量を分散させるようにしましょう。
- 床材にキズが付くのを防ぐために、いすの足などにはフェルトを付けましょう。
2. たたみ
日常のお手入れ
- たたみは直射日光にさらされると黄色く変化するので注意が必要です。また、カーペットを上に敷くと、たたみを蒸らしダニやカビの発生の原因となり、衛生面からみて望ましくありません。
- たたみの目はホコリがたまりやすいので、掃除機やほうきで毎日お掃除しましょう。その際、たたみを傷めないように目に沿って掃除機やほうきを動かしましょう。さらに念入りにホコリを取り除きたい場合は、乾拭きするときれいになります。
- 掃除機でも、乾拭きでも目にホコリが残ってしまう場合は、お湯で固く絞った雑巾で拭くときれいになります。住居用洗剤(酢でも可)をぬるま湯で薄め、布で浸して固く絞った布で拭くとさらにきれいになります。たたみは湿気を嫌うためお掃除の最後にはしっかりと乾拭きを行ってください。
※拭き掃除の際も、掃除機やほうきと同様にたたみの目に沿って行ってください。
【エコクリーニング】
ほうきで掃除をする時に、しっかりと絞ったお茶の葉をまいて一緒に掃くと目の中の細かなホコリがよくとれます。掃いた後は、乾いた雑巾で拭くのもお忘れなく。
【たたみ干し】
昔は大掃除の風物詩でもあったたたみ干しですが、最近は干す場所が少ないせいかめっきり見かけなくなりました。もしお住まいにたたみを干す場所がなくても、たたみを上げて、ビンや缶などを置きたたみの裏に空気を通すだけでも効果があります。
補修方法
| シミ | 塩素系漂白剤を水で薄めて綿棒でシミ部分に塗ると、数分で脱色されてきれいになります。 ※漂白剤の濃度が高すぎるとたたみの青さまで漂白してしまうのでご注意ください。 |
|---|---|
醤油・油などを こぼした時 |
粉末の洗剤・クレンザーをふりかけ、じゅうたんに液体を吸い取らせた後、掃除機で処理して、固く絞った布で何度も拭きます。最後に乾拭きをしっかりとします。 |
| クレヨンがついた時 | ごく少量のクリームクレンザーを乾いた布につけ、たたみを傷つけないように丁寧にこすります。 |
| フェルトペンがついた時 | 油性の場合はラッカー薄め液(マニキュアの除光液でも可)で拭き取ります。 水性の場合はクリームクレンザーで拭き取ります。 |
| へこみ | へこんだ部分に濡れたタオルを当て、アイロンをかけて直します。 へこみがもどったらドライヤーなどで十分に乾かしてください。 |
| 小さな焼けコゲ | 消毒液をたっぷり含ませたタオルで、たたきながら脱色します。 |
| 大きな焼けコゲ | (1)コゲた部分を切り取ります。 (2)切り取った部分よりやや大きめの切れ端にアイロンボンドをつけます(たたみ屋さんから分けてもらうとよいでしょう。) (3)たたみの目に合わせて押し込んでください。 (4)その上からアイロンをかけます。 |
| 縁の汚れ | (1)古い歯ブラシに、水で薄めた中性洗剤をつけて軽くこすります。 (2)蒸しタオルでたたいて乾拭きします。 |
| カビ | たたみ干しをして湿気を取った後、消毒用アルコールを布にしみ込ませ、カビを拭き取ってから掃除機で吸い取り、風を通して乾燥させます。必ずマスクとゴム手袋を着けて行います。 |
3. ビニール系の床(クッションフロアなど)
日常のお手入れ
- 掃除機でゴミを取り、固く絞った雑巾で拭き掃除をしましょう。
- 汚れが表面から内部の発泡層にしみ込むと取れにくくなるので、汚れたらすぐに拭き取りましょう。
- 定期的にクッションフロア用ワックスで磨くと長持ちします。
補修方法
| 汚れ | 中性洗剤をお湯で薄め、ムラなく塗ります。10~20分して汚れが浮いたら、ブラシなどでこすり落とします。よく絞った雑巾で、洗剤分を残さないように拭き取ってください。床が乾いたら、水性ワックスを2~3度塗ります。 ※濡らすと水が浸入しやすく、はがれることもあるので、継ぎ目や端部には気をつけましょう。 |
|---|---|
| 隅部のはがれ | 劣化した接着剤をヘラなどではがし、クッションフロア用接着剤を塗ります。 半日ほど重石をして定着させます。はがれを放っておくと範囲が広がっていくので、そり癖がつく前に補修しましょう。 |
| 劣化による割れ | 経年劣化により表面が固くなると、割れやすくなります。人の動線上で割れが生じた場合は張替えましょう。 大掛かりな作業となる場合は“リフォーム倶楽部オネスト”までご相談ください。 |

- 熱に弱いので、熱いものを直接置かないようにし、タバコの火にも注意してください。
- 重いものやゴム製品(家具のゴム製脚キャップなど)を長期間床の上に置くと、へこみや跡がつき、元に戻らなくなるので注意しましょう。
- 表面がやわらかいので重いものや尖ったものを落とさないよう気を付けましょう。
4. 玄関床(鉄平石・つや消しタイル・磁器質タイル)
日常のお手入れ
- 屋外からの砂や泥が主な汚れです。ほうきなどで掃きましょう。玄関マットを置いたり、庭先やポーチの砂や泥を掃除するのも有効です。
- 湿らせた新聞紙をちぎって床にまき、ほうきで掃くと細かいホコリや砂まできれいになります。
- 1週刊に1度は、ポーチの水洗いをしましょう。
※寒冷地では、冬の水洗いは凍結のおそれがあるので避けます。
※人造大理石・天然石(光沢のある床材)は水で濡らすと光沢が失われるため乾拭きします。
【ワックス掛け】
- ホコリをそのままにしておくと、湿気を吸ってシミの原因になってしまいます。ブラシや羽ぼうきでこまめにホコリを払いましょう。
- 落ちにくい汚れは消しゴムか食パンでこすり落とします。もし落ちないようなら、住居用洗剤を薄めたぬるま湯を布に含ませ、上からたたくようにして拭き取り、表面を傷めないように注意しながら、仕上げに乾いたきれいな布で拭きます。水拭きは汚れがしみ込んでしまわないようご注意を。